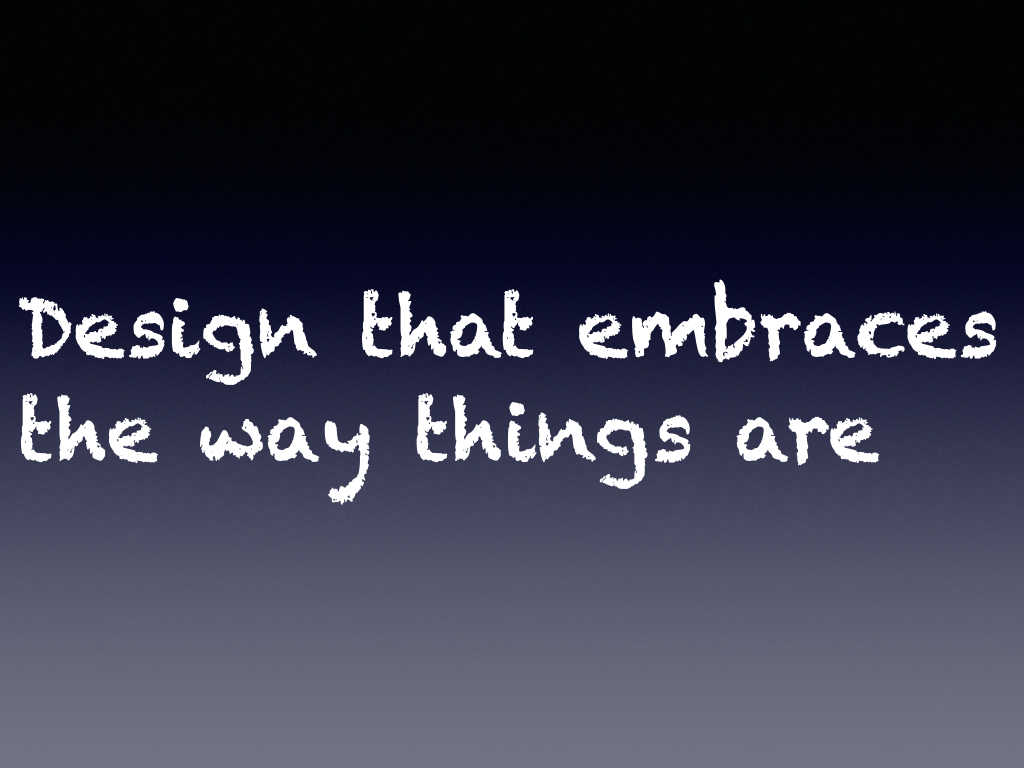「うけとめていく」という言葉には、過去と現在のあるがままを「うけとめる」ということ、
それを踏まえて前に向かって「いく」という行為の意味が含まれている。
あらゆる災いに対して大きな環境の変化に直面したとき、その状況を元に戻そうとしても、
時間軸そのものは過去に戻せず、前に進んでいくことと向き合わざるを得ない。ある大きな変化は、
時間がゆっくり流れていけば遠い未来に起こりうることが早回しされて、突如として訪れたものと
捉えることもできる。そうするとその状況との対峙の仕方は、元に戻そうというするのではなく、
早回しされて突如として訪れた未来をうけとめることから始めざるを得ない。
復興という言葉があるが、早回しで訪れた未来をつくっていく姿勢で対応せざるを得ないため、
元に戻すという意識では、起こった変化に対応できない。防災という観点から、身を守るという観点から、
日常の備えというものを考える場合、実は、すぐに訪れないかもしれない遠い未来の状況を想定することが重要なのである。それらを想定した上で早めに打てる手を打っていけば良いのだけれど、
扱うものの質量が大きければ大きいほど、対応への手間やコストがかかる。
よって、対応しやすい状況であり続けるためには、質量が大きなものを抱えないようにすることが望ましい。
この考え方が正しいとすると、
巨大な構造物で形成されている都市のありようは「うけとめていく」ことが困難なものであり、
もはや「うけとめきれない」ものになっているといえる。
この先どのようにしていけば良いのかという要点は2つあって、
1つは「うけとめきれない」ようなものをつくらないこと、
もう一つは、すでにある「うけとめきれない」ものをどう「うけとめていく」かということである。
一つ目は今後の姿勢しだいで対応していけるかもしれないように思えるものの、
二つ目については手遅れかもしれないと予感させる現象があちらこちらで生じている気がする。
「うけとめていく」デザインをキーワードにして、考えていることを少しずつ記述していきます。
その前書きはこちら→ 試論:「うけとめていく」デザイン連携活動
「うけとめていく」デザインを英語に翻訳する場合
次のようなフレーズが適切であると考えています。
“Design that embraces the way things are”